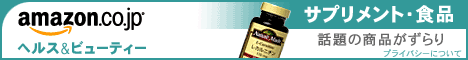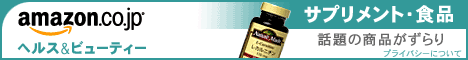◆ 土俵出て 市長救命中の女性に
「女人禁制」の伝統よりも、命の方が大事やと思うんやけど、こんな状態でも「土俵から下りて」って言うんやな。
しかも、調べて見たら「女人禁制」は「伝統」でも何でもなかったっちゅう話やし。
ほんま、相撲協会ってのはとんでもない組織です。
京都府舞鶴市で4日に開催された大相撲舞鶴場所で、土俵上で多々見良三市長(67)があいさつ中に倒れ、心臓マッサージなど救命処置をしていた女性に、女性は土俵から下りるようにとの場内アナウンスが数回行われたことが複数の観客の証言などで同日分かった。主催した実行委員会は「会場に待機していた消防署員と処置を交代したのでアナウンスが行われた」と説明している。
舞鶴場所は、同市上安久の舞鶴文化公園体育館であり、多々見市長は幕内と横綱の土俵入り後、午後2時すぎに土俵上であいさつに立った。途中で意識を失い、後方にそのまま倒れた。
複数の観客などによると、観客席から女性数人が土俵に上がり、心臓マッサージなどをしていた際、「女性の方は土俵から下りてください」とアナウンスが数回行われたという。
実行委の説明では、待機していた消防署員が自動体外式除細動器(AED)を持って処置を交代したため、日本相撲協会の関係者が「下りてください」とアナウンスしたとしている。
実行委によると、協会の担当者は「5日に会議にかけて正式に回答する」と話してるという。協会は過去に太田房江元大阪府知事が春場所優勝力士に知事賞を贈呈するのを断るなど土俵に女性が上がることを認めていない。
関連動画↓
大相撲舞鶴場所、舞鶴市長倒れ、救命女性に「女性は土俵から降りて下さい」とアナウンス
こんな状況で女性がどうとか言うてる場合やないがな。
だいたい、女性は生理がある。
血を流すのは穢れ、不浄。
って事で、土俵は「女人禁制」って事ってなってるけど、江戸時代には…
女相撲
女相撲(おんなずもう)とは、女の取り組みによる相撲を見せることを目的とする興行である。なお、この興行としての女相撲と日本各地に残る民俗ないし神事としての女相撲との間に直接の関係はない。
概略
江戸中期18世紀中ごろから流行した。当初女同士の取り組みで興行したが、美人が少なく飽きられたため、男の盲人との取り組みを始めて評判になった。大関・関脇などのシステムは男の相撲に準じており、しこ名には「姥が里」「色気取」「玉の越(玉の輿の洒落)」「乳が張」「腹櫓(はらやぐら)」などの珍名がみられる。
明治5年には、男女の取り組み・女力士の裸体が禁止されたため、シャツや水着が使われることもあった(それまで男同様全裸にまわしなど、少なくとも上半身は裸だった)。明治中期以降現れた複数の女相撲の一座には全国興行を行う興行団もあったという。その後昭和30年代後半まで九州に女相撲の興行団が残っていたらしい。また第二次大戦後に生まれた「女子プロレス」はこれら女相撲と同系統のものだという。
ってのがあったわけで、同じ土俵で女性も相撲をとってた。
結局、「文明開化」の流れで、こんな事をやってると西洋にバカにされるって事で、色んな理屈をつけてストリップ相撲を禁止したに過ぎんねんな。
この相撲の「女人禁制」に関して…
相撲における「女人禁制の伝統」について
概要
相撲は,神道との関わりを理由に,土俵上に女性を上げないという姿勢をとっており,それは「伝統」とされている。しかし相撲の歴史をひも解いてみると,女性と相撲は古来より密接な関係を保ってきたことが明らかになる。宗教・差別・相撲の歴史などの諸側面・諸次元から相撲における「女人禁制の伝統」を批判的に検証することによって,「相撲は神道との関わりがあるから女性を排除する」という論理が,明治期以降に,相撲界による地位向上などの企図にもとづいて虚構されたものであるという帰結が導き出される。これは,「性別役割分業」がすぐれて近代的所産(ないし近代における再編強化)であるという社会学あるいは女性(史)学の基本仮説を,文化(スポーツ)領域においても実証するものであろう。
はじめに
平成19年(2007年)9月19日大相撲秋場所11日目の一番(「豪風対豪栄道」戟)で一人の女性が土俵に上がるという「事件」があり,マス・メディアで大きく取り上げられることとなった。日刊スポーツは,「7世紀から続く約1400年の大相撲の歴史の中で初めて,土俵の女人禁制が破られるというハプニングが起きた」,と書いた。
しかし,この種の評論は,明らかに疑わしいものである。
日本の史書に初めて「相撲」という文字が登場するのは采女による女相撲の記事であるし,江戸時代には盛んに女相撲が行われていたという事実がある。また,現在のような「俵」で仕切られた土俵が登場したのは江戸時代のことである。
しかし相撲の女人禁制の「伝統」が疑われることはほとんどない。筆者自身も相撲について研究するまでは,15年間相撲に携わり指導も行ってきたが,一般的に言われる相撲の女人禁制について疑いを持つことはなかった。「国技」「伝統」「神道」などと言われてしまうと,信じざるを得ないというのが正直なところであった。そこで本稿では,語り継がれてきた相撲の「女人禁制の伝統」を批判的に検証していく。
てな論文があるんで、詳しい話はリンク先を読んで下さい。
だいたい、日本の最高神は天照大御神っちゅう女神やし、巫女だの何だのもおったわけで、そもそも「穢れ」なんてもんが後付けなんは明白やねん。
何にしても、「女人禁制」の伝統うんぬんの前に、人としてこんな事を言える事がどうにもおかしいんで、相撲協会は女性を土俵から下ろすよりも、理事会の役員が全員下りて、根本的に変えるべきですな。
だいたい、「女性は土俵から降りて下さい」って言うとるくせに、腐るほどおる男がクソの役にも立ってないって事を恥じろっちゅうの。
ほんま、情けないやら腹立たしいやら、どうにも困った組織ですな。
大相撲春巡業 多々見良三市長救命後に土俵に大量の塩をまく 市長はくもくも膜下出血で手術成功も1ヶ月の安静
追記
土俵に大量の塩まく 女性らが倒れた市長救命後 舞鶴
力士が土俵上でケガをした場合でも塩をまくみたいやから、市長が倒れたんで塩をまいたんやろうけど、「女性は土俵から降りて下さい」ってアナウンスして大量に塩をまいたら、女性が土俵にあがって土俵が穢れたからそれを清めたとしか見えんわな。
京都府舞鶴市で開かれていた大相撲の春巡業で、土俵上でのあいさつ中に倒れた多々見(たたみ)良三市長(67)を救命中の複数の女性に対し、土俵から降りるよう場内アナウンスがあった問題で、救命行動後に、大量の塩がまかれていたことがわかった。
複数の観客によると、女性を含む救護にあたった人たちが土俵から降りた後、相撲協会関係者が大量に塩をまいていた。
大相撲では、稽古中や本場所の取組中に力士がけがをしたり、体の一部を痛めたりしたようなときに塩をまくことがよくある。日本相撲協会の広報担当は取材に「確認はしていないが、女性が上がったからまいたのではないと思う」と話した。
映像ニュースはコチラ↓
「土俵から降りて」市長を救命の女性は看護資格あり、その後大量の塩撒かれる
「女性が上がったからまいたのではないと思う」って言うとかんと怒られるから言うとるだけで、あのアナウンスがある以上、それは通らんわな。
だいたい…
観客の60代女性は「周りにいる男性がおろおろしている中で、複数の女性がすばやく救命措置をしていたので立派だった」。場内アナウンスについては「女人禁制の伝統があるのだろうが、人命救助にかかわることであり許されない。救助の手を止めていたらどうなっていたことか」と話した。
男は糞の役にも立っとらんのに何をぬかしとるんやろね。
そこまで言うなら、万全の救護体制を敷いとけっちゅうの。
その助けられた市長は…
舞鶴市「女性にお礼を伝えたい」土俵で救命措置 くも膜下出血で倒れた市長に
舞鶴市広聴広報課によると、多々見良三市長は精密検査の結果、くも膜下出血と診断された。手術後の容体は安定しているが、およそ1カ月安静と入院が必要だという。この間、堤茂(つつみ・しげる)副市長が職務を代行することになった。
救命措置をした女性が誰なのか、舞鶴市ではまだ把握していないという。広聴広報課の三輪紀子課長は「市長に対応をしていただいた女性に大変感謝している。誰か分かればお礼を申し上げたい」と、ハフポスト日本版の取材に答えた。
くも膜下出血やったと。
1分1秒を争うのに、男も女もないわな。
舞鶴市がお礼を伝えたいって言うてるけど、相撲協会からも謝罪とお礼を伝えとけっちゅうの。
何にしても、こんな組織が公益財団法人ってのもおかしな話なんで、一般財団法人にして、ちゃんと税金を納めるようにさせるべきですな。
詳細記事&コメント投稿

女人禁制 (歴史文化ライブラリー)
次の記事
TOPに戻る
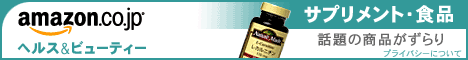


ぶんぐ占い
ぶんぐのぶろぐ
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP