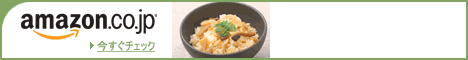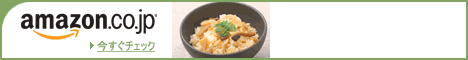◆ 聖徳太子 指導要領で復活へ
消したり、復活させたり忙しいこって。
文部科学省が2月に公表した中学校の次期学習指導要領改定案で、現行の「聖徳太子」を「厩戸王(うまやどのおう)」に変更したことについて、文科省が学校現場に混乱を招く恐れがあるなどとして、現行の表記に戻す方向で最終調整していることが19日、関係者への取材で分かった。
聖徳太子の話は2013年にも取り上げとるんやけど…
教科書に「聖徳太子は実在したか」って記述があるらしい
1000年以上「聖徳太子」って呼んでるのに、今更なくす方がおかしいねん。
文科省は、歴史学では「厩戸王」が一般的で、「聖徳太子」は没後の呼称だが、伝記などで触れる機会が多いとしている。
没後の呼称の何がいかんのかさっぱり分からん。
「昭和天皇」にしたって没後の呼称なわけで、今までそうやったのに、正式名がどうたらって言うてもしゃあないがな。
歴史学では「厩戸王」一般的か知らんけど、庶民からしたら没後の呼称の「聖徳太子」の方が一般的やねん。
「士農工商」が教科書から消えてるらしい
ってのも取り上げたけど、どうにも発想が左に巻いてるねんな。
戦前の歴史教育を否定するってとこから入ってるから、おかしな方向に話が進む。
しかも、中国、朝鮮半島寄りやからタチが悪い。
改定案で消えた江戸幕府の対外政策である「鎖国」も復活させる方向。
「鎖国」も復活すんのかい(笑)
これも鎖国が消えた時に書いたけど…
◆ 消えゆく「鎖国」「士農工商」
「鎖国」がなくなったらペリーが何しに来たか教え難いっちゅうの。
ちゅうか、「鎖国はなかった」にしといて、ペリーは「開国しに来た」は残してたんやからなぁ(呆)
ちゅうか、聖徳太子が存在したかどうか、鎖国はあったのかなかったのかってのを考えるのは、大学に入って歴史学を専攻してからでええねん。
どうせ、義務教育レベルじゃ歴史の流れを教えるだけで精一杯で、そういう細かいとこまで教えてる時間はないんやから。
それやのに、皇国史観の否定とか、どうにも左に巻いたヤツらがおかしな方向に持って行こうとする。
何にしても、これで子供に「聖徳太子って何?」って言われる事がなくなったのは良かったです。
とにかく、劇的に変更されると親子間で話がかみ合わんようになるんで、左に巻いた思想を織り込むの結構やけど、その辺は慎重にして欲しいもんです。
詳細記事&コメント投稿

ここまで変わった日本史教科書
前の記事
次の記事
TOPに戻る
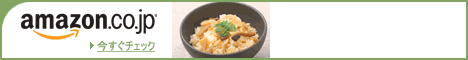


ぶんぐ占い
ぶんぐのぶろぐ
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP