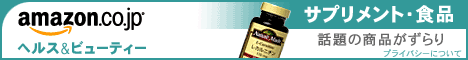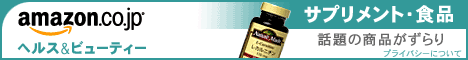◆ 古代人の共食い 儀礼目的か
古代人の「食人」が食料の為だけやなくて、儀式の側面もあるって研究するまでもないやろ。
現生人類を含む古代の人類が人肉を食べる食人(カニバリズム)をしていたのは、栄養価の高い食事を取るためというより儀礼的な目的のためだった可能性の方が高いとする異色の研究論文が6日、発表された。
現代人でも火葬後に骨を食べたりする人もおるわけで、それも広義の「食人」。
儀礼目的っちゅうか、亡くなった人を体内に取り込むってのは、実行するせんは別にして、そういう「感覚」は人間誰にでも備わってるんちゃう?
古代人に限らず日本でも薩摩藩なんか、戦の後に相手の武将の肝を食うと強くなれるっちゅうて、殺した後に肝を食うてたみたいやしな。
明治になっても…
鹿児島県
薩摩隼人が日常的に行っている競技が「ひえもんとり」です。ひえもんとりとは、死刑囚の遺体に数人でかぶりつき、皮膚や肉を噛み千切って、一番早く胆嚢を取り出したものが勝ちとなる競技です。娯楽の少ない鹿児島県では、老若男女分け隔てなく参加できるひえもんとりはとても人気のある競技で、週末は県民こぞってひえもんとりに熱中します。なお、最も早く胆嚢を取り出した選手にはサツマイモが与えられます。
「ひえもんとり」なんっちゅう風習があったみたいやし。
さすがにこれは引くけど…
どっちにしても、人が人を食うのは、食料ってよりは儀式ってのは研究するまでもないやろ。
そもそも、人が人を食料にするには手間がかかり過ぎる。
肉を食うなら、人よりももっと手っ取り早い動物がおるから、いくら古代人でも「食料にする」って発想にはなかなかならんやろ。
よっぽど獲物がおらんとか、極限状態になれば生きる為に「食料」にする事はあるやろうけど、それは現代人でも同じ。
そもそも…
英科学誌ネイチャー(Nature)系オンライン科学誌「サイエンティフィック・リポーツ(Scientific Reports)」に発表された今回の研究は、先史時代の食人は広く考えられているよりまれではなかったものの栄養的には得るところが比較的少ない危険な企てだったとしている。
研究では人体の部位ごとのカロリー値を算出した。同じ重さで比較すると野生のウマ、クマ、イノシシなどは、ほぼ骨と皮と筋肉だけのぜい肉のない体だった人類の祖先よりも脂質とタンパク質のカロリーが3倍以上もあったという。
古代人が「栄養」なんか考えんやろ(笑)
何にしても、「食人」を研究するなら、日本の隣に未だに食人文化が残ってる国があるから、それを研究した方が早いと思う。
「ヒト」やなくて「ヒトモドキ」かもしれんけど。
詳細記事&コメント投稿

ヒトはなぜヒトを食べたか―生態人類学から見た文化の起源
前の記事
◆今日のボツネタ◆
TOPに戻る
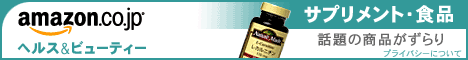


ぶんぐ占い
ぶんぐのぶろぐ
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP