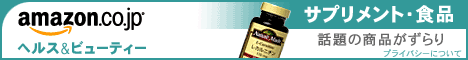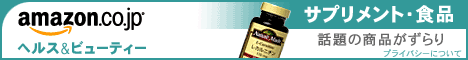全国で児童虐待の対応件数が増え続けている。虐待で命を落とした子どもも、2016年度だけで77人に上ったことが、厚生労働省による30日の発表でわかった。児童相談所(児相)や市町村が関与していたのに事件を防げなかったケースも目立ち、関係機関の連携強化の重要性が改めて浮かび上がった形だ。
「県の児相から虐待通告の連絡を受けたのに、緊急性なしと判断してしまった」
16年4月、奈良県生駒市で男児(当時2歳)が虐待死した事案の対応について、市の担当者はこう振り返った。男児は父親(41)(監禁致死罪などで実刑確定)にプラスチック製のケースに閉じこめられて死亡した。
男児が死亡する約4か月前には、県の児相が「子どもの泣き声がする」と虐待通告を受け、市に確認を依頼していた。しかし、市は家庭訪問をして母親と男児に面会した結果、虐待のリスクは高くないと判断。この家庭は、以前に乳児訪問を受け入れるなど市に協力的な態度を見せていたことから、市は「母親とは関係が築けている」と考えたという。
だが、県の検証部会がまとめた報告書は、この時期、母親は周囲に暴力を肯定する発言をしたり、男児にあざなどが確認されたりしていたと指摘している。
男児の死を防げなかったことについて、市の担当者は「家庭訪問で虐待のリスクが高まっていることを感じ取ることが出来なかった」と悔やんだ。
厚労省のまとめでは、16年度の虐待死のうち無理心中を除いた49人をみると、約3割にあたる14人は市町村や児相が関与していた。
大阪府松原市では15年12月、男児(当時3歳)が父親(37)(傷害致死罪などで実刑確定)から暴行を受けて死亡。男児の遺体は16年11月に山中で見つかった。
この男児について、市は乳幼児健診を受けていないことを把握していた。しかし、親から受診延期の連絡を受けていたことなどを理由に、一度も家庭訪問をしていなかった。
また、府の児相は男児の両親が過去に別の刑事事件で書類送検されていたことを市に伝えていなかった。この事件が不起訴となったことが理由だとしているが、府担当者は「きちんと情報を伝えていれば、市も違う対応ができたかもしれない」と振り返る。府の専門家部会の検証では、市と児相、警察との情報共有の強化の必要性が指摘された。
■生後1か月未満、半数の16人
一方、虐待死した0歳児を月齢別にみると、生後1か月未満が半数の16人を占めている。このうち12人は実母による加害で死亡した。厚労省によると、実母が加害者となるケースでは妊娠を周囲に相談できず、出産後に放置するケースがあるという。松原康雄・明治学院大学長(児童福祉論)は「転居など環境の変化によって虐待のリスクは刻々と変わる。危険な兆候を察知して子どもを守るためには、児相や市町村、警察などの関係機関が連携し、情報共有を徹底することが欠かせない」と話している。