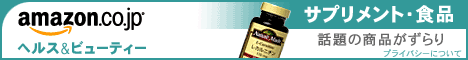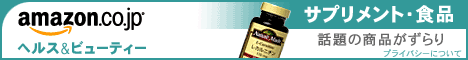全国の主要自治体を管轄する消防本部や消防局で、心肺停止の高齢者を救急搬送する際、現場で蘇生処置を希望しないとの意思が示された経験がある消防機関が全体の6割にあたる46機関あることが、毎日新聞のアンケートで分かった。さらに8割の60機関が蘇生不要の意思を受けた場合の対応で「苦慮する」と回答した。消防法令は蘇生措置の実施と、死亡と判断して搬送しない場合しか想定しておらず、蘇生中止に関する法的規定はない。救命任務と、本人の意思尊重との間で救急隊員が苦悩している現状が浮かんだ。
心肺停止時に患者本人または家族らの意思を受けて蘇生処置しないことを「DNAR」と呼ぶ。高齢者の場合、本人らに蘇生不要の意思があっても、動転した家族や入所先の施設職員らが慌てて救急要請する場合があり、現場で救急隊員がDNAR対応を迫られることが課題とされていた。
実態を調べるため、毎日新聞は昨年12月、東京消防庁と道府県庁所在市、政令市、中核市の計79消防機関に調査書を送り、74機関から回答があった。回答率は94%。質問は、末期がんなどの背景がある高齢者が心肺停止した場合のDNAR対応に限定した。
2016年4月以降、実際に現場で蘇生不要の意思が示されて対応に迷ったのは46機関。DNAR対応に独自の手順を定めた地域もあり、うち16機関で蘇生を中止した実例があった。件数は16年4月~17年9月で把握分だけで47件あった。
DNARの対応を「決めている」のは44機関で全体の6割。具体的には「本人の(蘇生不要の)希望や医師の指示があっても、家族を説得し心肺蘇生を継続する」が21機関と最も多く「かかりつけ医から中止の指示があれば心肺蘇生を中止する」は12機関だった。