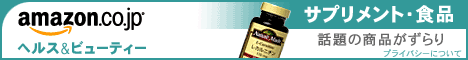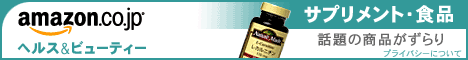

訴状によると、女性は、難病指定されている血液疾患「発作性夜間ヘモグロビン尿症」のため、2011年から、京大病院血液内科で治療を受けていた。16年4月、妊娠に伴い血栓症予防のため新薬「ソリリス」の投与を開始。同病院で8月1日に長男を出産後も通院していた。
同月22日、薬剤投与後に自宅で急激な発熱に見舞われた。京大病院の産科に連絡したが、対応した助産師は「乳腺炎と考えられる」とし、自宅安静を指示。しかし容体は悪化し、同病院に搬送されたが、翌23日に髄膜炎菌敗血症で死亡した。
ソリリスの添付文書には、重大な副作用として「髄膜炎菌感染症を誘発する」と記載されており、海外の死亡例を踏まえ、発熱や頭痛の際は抗菌剤の投与を求めている。
京大側は、今年5月の京都地裁の調停で「患者が重大な副作用情報を医師に知らせるべきで、医師は他の医師に対してまで周知する義務はない」としていた。
ソリリスの薬代は、年間約4,000万円かかる。そして、高額療養費返還制度の対象となり、4,000万ほとんど丸々が健康保険の保険者から支払われる。
ソリリスの効能は、溶血に伴い増加する血清乳酸脱水素酵素(LDH)値の低下、ヘモグロビンの安定化、および濃厚赤血球輸血単位数の減少などの指標(surrogate marker)の改善を根拠とした、溶血の抑制効果に過ぎない。血栓症の減少効果は、現時点では不明である。
つまり、この薬は、貧血の進行は抑えるらしいが、元気に長生きすることにつながるか否か、いまだ不明なのだ。そして、どのような状態のPNH患者につかうべきか、という絞り込みもなされていない。